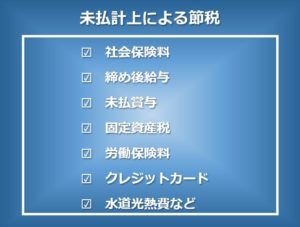期末に備品を購入すると節税になるのか
決算日が近くなると、30万円未満の備品の購入を勧められることがあります。少額減価償却資産とすることで、購入した年に全額を経費にできるのですが、3年間で経費にする一括償却資産の方が節税になる場合もあります。仕組みを理解することで、自社に最もメリットがある処理を選択できます。

1.三つの方法から選択できる
1年以上使用できる備品等で10万円以上のものは固定資産となります。通常は耐用年数の期間で減価償却しますが、取得価額が30万円未満の場合は少額減価償却資産(購入年に全額償却)、20万円未満の場合は一括償却資産(3年間で1/3ずつ償却)とすることもできます。経費に配分する年数が違うだけで、いずれも経費にできる総額は同じです。利益の状況、償却資産税(※)の負担、事務処理を考慮して処理方法を選択します。
<償却方法の比較>
| 通常の減価償却資産 | 一括償却資産 | 少額減価償却資産 | |
| おすすめしたい方 | 利益を減らしたくない方 | 償却資産税を増やしたくない方 | 今期の経費を増やしたい方 |
| 制度の趣旨 | 耐用年数に応じた費用配分 | 個別管理する事務負担への配慮 | 事務負担への配慮、少額資産の取得促進 |
| 取得価額 | 10万円以上 | 10万円以上20万円未満 | 10万円以上30万円未満 |
| 償却期間 | 耐用年数に応じた年数 | 3年間で1/3ずつ償却 | 購入年に全額償却 |
| 限度額 | なし | なし | 1年間で累計300万円まで |
| 対象者 | 全事業者 | 全事業者 | 中小企業等 |
| 償却資産税の課税 | 課税対象 | 対象外 | 課税対象 |
※償却資産税は市区町村の税金で、1月1日時点で所有する土地や家屋以外の事業用資産の評価額に対して税率1.4%で課税されます。
2.少額減価償却資産の要件
少額減価償却資産の主な要件は次の通りです。30万円未満というのは、299,999円までのことを指します。1年間で300万円に達するまで適用できます。
<主な要件>
- 取得価額が30万円未満の固定資産を取得して事業に使うこと
- 年間の少額減価償却資産の合計が300万円未満であること(開業年などで1年未満の場合は月割りにします)
- 青色申告書を提出する中小企業者等であること
- その他一定の要件
3.押さえておきたいポイント
適用にあたっては「正しい取得価額で判定しているか」、「償却資産税が課税されても良いか」を検討することがポイントとなります。
(1)取得価額は一単位ごとの金額で判定
30万円未満かどうかの判定は、通常一単位として取引される単位の金額で判定します。例えば応接セットであればテーブルと椅子が一組で取引されるものなので、それぞれの個別の金額ではなくセットの合計額で判定します。また、カーテンの場合は、カーテン1枚で機能するものではないので、1部屋ごとの合計額で判定します。勘違いしやすい部分なので、注意が必要です。

(2)金額判定時の消費税の取り扱い
30万円未満かどうかの判定にあたっての消費税の取扱いは、税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します。税抜経理は本体価格と消費税を分けて経理処理する方法で、税込経理は消費税を含めた金額で経理処理する方法です。以下のように金額の判定においては、税抜経理の方が有利となります。
<税込315,000円の場合>
| 消費税の経理方法 | 取得価額の判定 | 適用可否 |
| 税抜経理の場合 | 315,000円X100/110=286,363円 < 300,000円 | 可 |
| 税込経理の場合 | 315,000円 ≧ 300,000円 | 不可 |
(3)償却資産税の有無
少額減価償却資産は購入した年に全額経費にできますが、通常の固定資産と同様に、償却資産税が課税されます。一方、20万円未満の場合は一括償却資産を選択すると、償却資産税は課税されません。早期の償却を優先するか、償却資産税の回避を優先するか、利益の状況等に応じて選択すると良いでしょう。
4.おわりに
30万円未満の備品などを購入した場合には、処理方法が複数あります。自社の状況に合わせて、最もメリットのある処理を選択しましょう。