税理士試験の勉強方法で大事なこと
税理士試験の勉強をしていた頃に、科目選択や勉強方法について、考えていたことをまとめてみました。
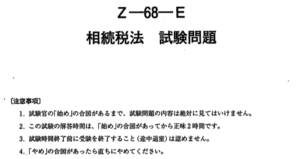
1.受験した科目
税理士試験は、会計2科目と税法3科目のあわせて5科目に合格すると、合格証書がもらえます。
私の場合、税法3科目は次の理由から選択しました。
| 科目 | 選択した理由 |
| 消費税法 | ・実務でよく使うため ・勉強のボリュームが比較的少なくて済むため ・税法で最初に受ける人が多く、合格しやすいと考えたため |
| 所得税法 | ・すべての人を対象とした身近な税目のため ・法人税法よりも面白かったため ・個人の資産に関する税金に強くなるため |
| 相続税法 | ・相続税法の合格者は少なく、武器になると考えたため ・個人の資産に関する税金に強くなるため |
5科目合格までにかかる期間は、平均8〜9年といわれており、私の場合は10年かかりました。あらためて振り返ると、延べ14回の受験をしていて、5勝9敗でした。勉強を始めた当初は「3年で合格する」決意だったのですが、想定通りには進まず、合格できない年が続いた時期はきつかったです。
| 2009年(H21年) | 財務諸表論 〇 | 簿記論 X |
| 2010年(H22年) | 簿記論 X | 消費税法 X |
| 2011年(H23年) | 簿記論 〇 | 消費税法 〇 |
| 2012年(H24年) | 所得税法 X | |
| 2013年(H25年) | 所得税法 X | |
| 2014年(H26年) | 所得税法 X | |
| 2015年(H27年) | 所得税法 X | |
| 2016年(H28年) | 所得税法 〇 | 相続税法 X |
| 2017年(H29年) | 相続税法 X | |
| 2018年(H30年) | 相続税法 〇 |
1科目の合格するだけでも大変な試験なので、1年に1科目ずつ合格できる方は優秀だと思います。
2.勉強方法で大事なこと
合格するために大事だと思うことを4つあげてみました。
(1)必ず受験予備校を使う
相対試験なので合格者数は限られています。合格者のほとんどは、大手の受験校で勉強した人で占められています。受講料の負担は大きいですが、受験予備校を使わなければ合格できない試験です。私の場合、1科目15万円/年とすると、延べ14回なので200万円くらい使ったようです。
(2)合格レベルを知る
1年という長い期間をかけて勉強する試験です。「8月の試験日に、どのくらいのレベルになっていれば合格できるのか?」をわかった上で勉強しないと、合格レベルに到達できない可能性が高くなります。
10年くらい前までは、受験校から「合格体験記」の本が出版されていました。短期間で合格した人の勉強法や、合格するために取り組んだことなどが書いてあり、合格に必要な到達レベルがわかるので、参考になりました。今は出版されていないので、ネット情報やkindleでいろいろな人の合格者体験記を読んでおくとよいでしょう。
(3)書いて覚えることをやめる
税法理論の暗記方法について、覚え方は人それぞれですので、私の場合の暗記方法です。理論を書いて覚えようとすると時間がかかるので、暗記できる理論の数が少なくなるし、直前期の理論回しも不足してしまいます。
「声に出す」「頭でそらんじる」「文字を隠す」など暗記方法を工夫しましょう。
私の場合、クリアファイルを切ったものを使って、文字を隠して覚えたり、理論回しをしていました。

(4)直前期は予告理論を見ない
直前期のテストでは、受講生の負担を考慮して、出題される理論が予告されます。テストで良い点を取りたい気持ちはわかりますが、本番の試験に出題予告はありません。テストで良い点を取っても、本番で書けなければ意味がないのです。
直前期のテストでは、予告理論を見ないようにして、毎回本番だと思ってテストを受けましょう。なるべく多くの理論を覚えることにつながりますし、本番で覚えていない理論が出題された場合の練習にもなります。
3.おわりに
税理士の仕事は、経営者と直接接することができ、世の中のさまざまな仕事を知ることができる、面白い仕事です。試験勉強は長い期間になることが多いので、勉強方法を工夫したり、受験仲間をつくったり、楽しみを見つけながら取り組むと良いと思います。

